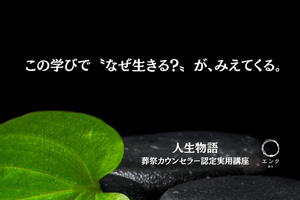未成年の相続の場合
- 2025/03/17
3
友人のご主人が昨年末に亡くなりました。
友人(故人の妻)と中学生の娘さんと小学生の息子さんを残されて。
これから相続手続きをしないといけないようなのですが、未成年の相続人だと家庭裁判所に申し立てて、代理人のような後見人というのをつけないといけないと言われました。
友人はもちろん保護者ですが、必ずつけないといけないのですか?子どもが2人いるとそれぞれにつかないといけないのですか?
回答者からの回答
山下さんのご説明のとおり、相続のとき特別代理人を立てなければならないケースなどでは、あらかじめ遺言を作成しておくことで、相続手続きの手間を大幅に削減することができます。
以前は、公正証書でないと意味がない(検認という手続きが必要なため)とも言われていましたが、現在は預託制度ができており、これを利用すれば検認は不要となっています。費用も数千円ですので、遺言があったほうがよいケースではご検討ください。
🔷自筆証書遺言の預託制度について
(法務省のウェブサイト)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
身近な親族を亡くし、何も手につかない心理状態のときに事務手続きで苦労しないためにも、いざというときのことについて平常時から考えておくことがとても大切です。
縁空では、毎月22日の20時〜月例Zoom勉強会を開いており、どなたでも参加できます(詳しくは縁空公式LINEでお伝えしています)。
2025/04/14

縁空のオケイ/勝 桂子
グルテンフリー歴9年(^^♪
一点、申し上げ忘れておりましたことがございますので、以下に補足いたします。
もしも故人が遺言を残しており、その内容によって遺産分割が指定されている場合には、遺産分割協議は不要となります。このため、相続人間で利益相反の問題が生じることもなく、遺産分割協議書の作成や特別代理人の選任も必要ありません。
2025/04/14
山下了美
相続手続きでは、相続人が複数いる場合、「遺産分割協議」を行い、誰がどの財産を受け取るかを話し合って決める必要があります。
しかし、今回のケースのように相続人の中に未成年者がいる場合には、注意が必要になります。民法の規定により、未成年者が法律行為(=遺産分割協議など)を行うには、法定代理人が必要です。
通常は親が法定代理人となりますが、以下のようなケースでは問題が生じます。
親もともに相続人であり、未成年の子どもも相続人である場合、親と子の利益が相反する関係になります。
つまり、親も利益を主張できる一方で、代理人として子どもの利益を守る立場になることはできません。
これは民法第108条の「利益相反行為の禁止」に該当します。
同一の法律行為について、当事者双方の代理人にはなれないと規定されています。
このような場合には、親に代わって未成年者の利益を守るために、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てる必要があります。
申立先:未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所
なお、未成年のお子さまが複数いる場合でも、1人の代理人が2人の子どもを同時に代理することはできません。
なぜなら、未成年者同士の間でも相続分をめぐって利益が対立する可能性があるためです。
したがって、それぞれの未成年者ごとに特別代理人を選任する必要があります。
2025/04/14
山下了美
![お坊さんが必ず答えてくれる相談サイト - hasunoha [ハスノハ]](https://enc-llc.jp/wp-content/themes/hasunomi/imgs/banner/banner_hasunoha.png)