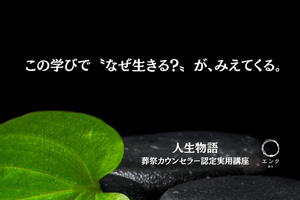借金まみれの父が急死しました。相続放棄するにはどうすればいいですか?
- 2025/06/14
2
借金まみれの父が急死しました。急逝したので、遺言はありません。
家庭裁判所に放棄の申述をしないと、自分たちに借金返済の取り立てが来るので放棄したいです。どのようにすればいいですか? 行政書士さんや司法書士さんに手続きを依頼しないといけないのでしょうか。
家庭裁判所のサイトを見て、必要書類(戸籍等)は揃えました。
申請書もダウンロードしてあります。
回答者からの回答
行政書士からの補足です。
もしも多忙で3ヵ月の期限に間に合いそうになく、申述書の提出を士業者に代理してもらう場合は、お早目に弁護士事務所等へご相談ください。
裁判所へ提出する書類ですので、「行政書士」には代理申請できません。
申請の代理だけであれば「司法書士」に代理をお願いすることもできます。ただし、期限が短いので放棄を専門に扱うかたでないと受任してもらえない可能性が高いです。
司法書士に依頼できるのは申述書の作成や必要書類の収集だけで、裁判所からの照会や債権者とのやり取りは、ご自身が行う必要があります。
事後のやりとりを含めて任せたい場合は、「弁護士」が適任です。
また、福中葬祭カウンセラーの回答中の「郵便切手(申述書提出時に必要)」については、返信用のものなのですが、裁判所によって求められる金額と枚数が異なりますので、必ず申請前に電話で確認するようにしましょう。
2025/06/18

縁空のオケイ/勝 桂子
グルテンフリー歴9年(^^♪
心中お察しいたします。
相続放棄は、原則として相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に行う必要があります。
(これは手続き完了期限ではなく、書類の提出期限ですので、手続きを開始すれば期限切れにはなりません)
既にご自身で必要書類を揃え、申請書もダウンロードされているとのことですので、基本的な準備は整っているようです。
あとはご自身で記入して、家庭裁判所へ提出するだけで大丈夫だと思います。
以下、相続放棄の手続きの一連の流れになります。
1. 必要書類の確認と準備:
・相続放棄申述書(ダウンロード済みのもの)
・亡くなられた方の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
・亡くなられた方の住民票の除票
・申述人(相続放棄をする方=相続人)の戸籍謄本
・その他、家庭裁判所から指示される書類(続柄を示す書類など)
・収入印紙、郵便切手(申述書提出時に必要)
2. 相続放棄申述書の記入:
・相続開始を知った日や相続放棄の理由などを具体的に記入
3. 家庭裁判所への提出:
・管轄の家庭裁判所に直接提出するか、郵送で提出
管轄の家庭裁判所とは、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
4.照会書・回答書のやり取り(必要に応じて):
家庭裁判所から、相続放棄の意思確認のための照会書が送られてくることがあります。その場合、指示に従って回答書を提出します。
5.相続放棄申述受理通知書の受領:
申述が受理されると、「相続放棄申述受理通知書」が交付されます。
これが相続放棄が認められた証明となります。
不明な点があれば、家庭裁判所の窓口に直接問い合わせて相談することも可能です。
また、もし3カ月の期限が迫っている・過ぎてしまった場合や、家庭裁判所とのやり取りに自信がない場合などは、一連の手続きが代行可能な弁護士や司法書士に相談されてもよいでしょう。
何はともあれ、早めの手続きをおすすめします。
2025/06/18
福中翔子
![お坊さんが必ず答えてくれる相談サイト - hasunoha [ハスノハ]](https://enc-llc.jp/wp-content/themes/hasunomi/imgs/banner/banner_hasunoha.png)