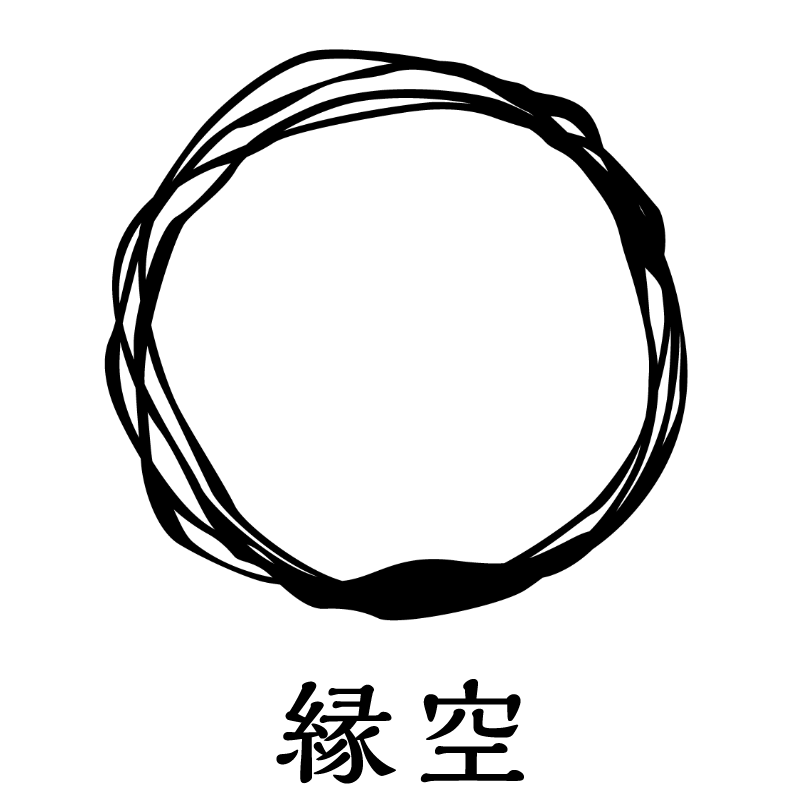「誰もがブッダになれる」とは、どういうことなのか?
じつは、「ブッダ」という言葉はお釈迦さまの国の言葉(パーリ語やサンスクリット語)では、「目覚めた人」、「悟った人」という意味。お釈迦さまの時代には仏教徒だけでなく、バラモン教徒(いまのヒンドゥ教)はもちろんのこと、ジャイナ教徒など、どの宗教の人でも使っていた言葉なのです。
漢字に訳されたあとに伝わってきた日本仏教に慣れ親しんでいる私たちは、「ブッダ」といえば釈迦牟尼、釈尊、ゴータマ・シッダールダという個人、つまり王子だったのにお城を出て仏教を開かれた人のことである、と思ってしまいがちです。しかしほんとうは、誰でも適切な師匠のもとで学べば知りうる智慧、人生の本質に〝気づいた人〟という意味なのです。
つまり、適切な師匠について学びさえすれば「誰でもブッダになれる」。そう教えているのが、仏教やヒンドゥー教、あるいは古代インドのヴェーダの教えなのです。
仏教はブッダと契約する宗教ではない。それなら哲学とどう違うの?
以前、在日トルコの人たちと、日本の僧侶や神職さんを集めて語らう会をしたことがあります。そのなかである日本人僧侶がトルコの皆さんに、こう説明されました。
「みんながブッダ、つまり悟った人になることをめざすのが仏教であり、釈尊ひとりをあがめる教えではないし、釈尊と契約をする宗教でもありません。だから日本の寺ではイスラーム教徒のかたも、ユダヤ教徒のかたも、坐禅をしてゆかれます」
と。すると、
「仏教というのは、釈迦牟尼ブッダと契約をする宗教ではないのですか?」
と、皆さんとても驚かれていました。そして、
「それでは仏教は、宗教ではなく、哲学や一種の思想のようなものにすぎないのではないですか?」
と問われました。
そのとき、かのお坊さまは、こう答えられました。
「いいえ。思想や哲学には、実践する動作(英語で、practiceと説明されていました)はありません。仏教には、読経や坐禅といった実践があります。だから、まぎれもなく宗教なのです」
気づくのは一瞬で可能。それなのに、〝気づいたと気づいてしまうこと〟で闇に堕ちてしまう、私たちの愚鈍さ
ほんとうの自分に気づくこと――。
縁空ブログの第1回でも述べたとおり、それは、特別な才能を必要とすることではありません。
誰でもそれをめざすことはでき、めざしはじめたらそれは、ゼロかイチか、つまり気づく才能があるかないかの二律背反なのではなく、〝その瞬間ごとに〟は誰でも、気づくことができるものです。
しかし、ほとんどの人は、気づいた瞬間があったとしても、気づいたという事実に狂喜してしまい、
「私は、ほかの人が気づかない悟りを得た!」
と高みに立つようになるので、気づくための眼が永遠に閉ざされてしまうのです。
「自分はほかの人とは違う。わかっている人間だ」
などと思いこめば傲慢となり、気づく前よりも〝瞬間の気づき〟を得づらくなってしまうことでしょう。
予定外のことが重なると、〝私のせいじゃないのに!〟と腹が立ってしまうことはありませんか?
私はシングル親として小学生3人を育てていたころ、夕飯を作り置きしていないのに、帰宅が21時になってしまったことが一度だけあります。
親しいヨガの先生の特別講座に、連続3講座のうち2講座目まで出て、夕方帰るつもりだったのです。
1講座目で身体をほぐし、2講座目が脳科学の座学、3講座目が集団ワークでした。2講座目を受けた時点で、「この流れで3講座目を受けると、ほんとうに何かに気づくことができそう」という予感がして、その日のその日で夜の回を追加したのです。結果、〝気づく〟ことができたので、最後まで受講してよかったのですが……
家族にはLINEで、乾物の置き場を伝え、温めて食べておいてほしいと伝えたつもりでした。
ところが3講座目が終わってから端末を見ると、不具合で送信できていませんでした。すぐに再送信しようとしましたが、通信会社がその日に限って不具合を起こしていて、いくらトライしてもメッセージを送ることができませんでした。そうこうするうちにスマートフォンの電源がなくなり、電話連絡すらすることができなくなり、急いで帰宅したものの21時になっていたのです。
帰宅すると、高学年の女児たちはスナック菓子などで適当におなかをふくらませていましたが、低学年の男児は疲れ果てて居間でうたた寝していました。
前日までの私なら、おそらくなかば苛立ちながら、「何度もLINEを送ったのに不具合で届かなくて。どうして何かしら食べておいてくれなかったの!」と強く言ってしまっていたでしょう。長女が不登校で、ただでさえ〝あの家はシングル親だから〟と思われてしまうので、当時の私は、「規則正しく食事を出し、早い時間に子どもたちを寝かせること」を最優先に生きていたのです。
たしかに今日は、私自身のワガママで夜まで講座を追加したけれど、ちゃんとみんなの顔を思い浮かべて、棚にしまってあるアレとコレを温めるくらいなら小学生でもできるよねと考え、連絡しようとしていたのです。通信不具合は、私のせいではありません。手を尽くしたのに、こうなってしまった。こんなことは今まで一度もなかったのだから、少しは頭を使って自分で温めて食べられるものを探したりしてほしかった、と、憤ってもしょうがないのに腹を立てていたはずです。
〝目の前にある事実〟をそのまま見る。それだけで、〝瞬間の気づき〟は得られる
ところがその日、待ちくたびれてうたた寝している末っ子を見て思ったことは、
「いま、空腹の小学生男児がここにいる」
ということだけでした。そして、
「ごめん、お腹すいちゃったよね。すぐ冷凍ご飯温めるから」
と言って支度を始めました。怒りが沸いてこないということは、なんと心地よいことなのでしょう!
よくよく考えてみれば、「なんで、少しは頭をつかって何か温めて食べなかったの!」と怒鳴ったところで、彼の空腹は改善しません。私の帰りが遅いのを心配し、不安にもなっていたかもしれないところへ、イヤな思いをさせるだけです。そんな簡単なことに、前日までの私はおそらく気がつかなかったのです。
支度をしながら、きのうまでの自分ならきっとこうなったであろうことを思い浮かべ、なぜ過去の自分はそんなに憤ってしまっていたのか? を考えました。瞬間的にわかったことは、いままでの私は、「ちゃんと努力した自分をアピールしたかっただけだった」ということでした。
その日の2講座目で脳科学の先生から教わったことは、ペットボトルに水がいくらか入っているとき、どう思うかの話でした。ドラッガー理論でよくある、「もうこんなに減っている」なのか、「まだこんなにある」なのかの違いに似た話です。
でも、その日の話は、「もう」を「まだ」に転換することを教えるものではありませんでした。
第三の道、「いま、ペットボトルに水が何センチ、あるいは何分の一入っているな」と、事実だけをみる道でした。
まさしく、釈尊の教えと同じじゃないか、と思いました。
その理論を言葉で聴いただけだったら、私はその感覚を現実に使ってみることはなかったでしょう。3講座目のワークでその効果を実践し、そのうえ幸運なことに、その日〝予想外の通信不具合〟が重なったために、直後にまさに「事実だけをみる」ということを実践することができ、かつてないほど平穏な時間をもつことができるようになったのだと思います。その後も、ことあるごとに〝事実だけをみる〟という方法をくりかえして今にいたります。
日々の実践を伴う、宗教の重要性
私の体験談は、「腹をすかせた男児に、なぜ工夫をして食べなかったかと怒鳴ったところで、腹はふくれない」という単純な話だったので、「ものすごい発見をした!」と高揚するような話でもなく、傲慢になるような流れにもなりませんでした。
また私の場合は葬祭カウンセラーという仕事がら、周囲にたくさんの宗教者がいて、法話会に出ることなども頻繁にあり、〝気づきの確認〟をさせていただく機会に恵まれていたと思います。
これがもし数十人を束ねる部課長や社長さんなら、「これで一大改革ができる!」「ほかの経営者にはない気づきを得た」などと、たった一度の気づきを誇らしく思うがために、もしかしたら、実るほどに頭を垂れることを忘れてしまう方向へいってしまわれるかたも、いらっしゃるかもしれません。
人は、大半の人が気づかないことに気づくと嬉しくなり、高みに立ってしまいがちです。
だからこそ、前半の話にあったように、宗教は、必ず実践(=Practice)を伴うのです。
師匠や仲間とともに語らい、日々「実践できているかどうか」を確認しあい、よりよく生きるために人々が〝宗とする教え〟。それこそが「宗教」なのです。
仏教僧侶も、上座部の国においては「サンガ」という5人以上のグループをつくらないと布教ができないことになっていると聞きます。日本のように、ご住職とその子息だけで多くのお寺が維持されているのは、特殊な例ともいえます。そうなってしまった事情については、また別記事でお話ししましょう。
縁空の葬祭カウンセラーには、宗教者と、専門職と、一般のかたとがバランスよく集っています。
日々の気づきを得てブッダをめざしてみたい、と感じるかたはぜひ、葬祭カウンセラー認定実用講座へいらしてください。
🔷尽きない生涯学習を探究したいかたへ:葬祭カウンセラーとは?
最後までお読みくださり、ありがとうございます。
このようなテーマを気に入ってくださるかたに、縁空の葬祭カウンセラー認定実用講座をオススメします。
葬送儀礼についての民俗学的な知識を学び、日本人として生まれたことへの理解を深められる講座です。
知識を得て認定されることは、最終目的ではありません。葬祭カウンセラー事例研究グループでは、縁空ブログがテーマにしているようなさまざまな「答えのない問い」に向きあい、語らい続けるほんとうの意味での生涯学習を継続します。
事例研究グループの運営は、任意のご喜捨のみでしています。認定料も、年会費も一切徴収しません。
そのため本講座(動画10本の試聴+効果測定の8割以上正解で認定)の受講料は少々高めに設定しております。それでも、ほかで聴くことのできない全10回の動画講座が、各回あたり飲み会に二次会まで参加した程度の料金です。クレジットカード払いでしたら24回までの分割も可能です。別途ご相談いただければ学割・生活保護割引も適用いたします。
しかも、ひとりでも多くのかたに葬祭の学びを得ていただきたいので、「同居のご家族」は追加料金なしでご受講いただくことができます(100%引きクーポンを進呈)。
🔷ほぼ月に一度のペースで、事例研究Zoomを開催しております。縁空公式LINEに友だち登録いただければ、開催情報が届きます。また毎回のZoomの終盤で、本講座の割引クーポンコードをお知らせしておりますので、受講をご検討のかたはぜひ、まずは事例研究Zoomで雰囲気を知ってからお申し込みください。
🔷Facebook内のプライベートグループ「葬祭カウンセラー事例研究グループ」も、葬祭カウンセラーにご関心のあるかたどなたでも参加できます。プライベートグループのため、こちらから「参加申請」をいただいたうえで承認させていただきます。
🔷講座詳細は、当ウェブサイトトップページ画像内の「縁空塾」でコエテコカレッジにジャンプし、なかほどの「販売講座一覧」から「葬祭カウンセラー認定実用講座」で、ご確認ください。